�������ʿ��дط��Τ�ΤΤߡ�
��ϡ����ޤǸ���ԤȤ��ơ����Ф�Ҳ𤹤�ؽ���ʸ���ܤ��Ƥ��ޤ����������Ǥϡ��䤬���������ʸ�ȡ����γ��פ�Ҳ𤷤ޤ�������ޤǤλ������ϡ�ʸ������ؤδ������������Ū�ʳؽ���ʸ�Ф���Ǥ��������¤ǤΥե�����ɥ���������켡�����������ơ�ʿ�פ�ʸ��ɽ���ǽƤ��ޤ����äˡ����Ф���ͥ����˴ؤ������ƤΤ�Τ�¿���Ǥ��ˡ���ʸ�˴ؤ��Ƥ���ؿ�ۤ�Ȥ����ơ��ޤ�������˴ؤ��ƤϽ�Ź��Ȥ���������Ǥ��ޤ��Τǡ���̣���������Ϥ����ˤʤäƤ������������ո��������ۤ��Ԥ����Ƥ��ޤ���
����
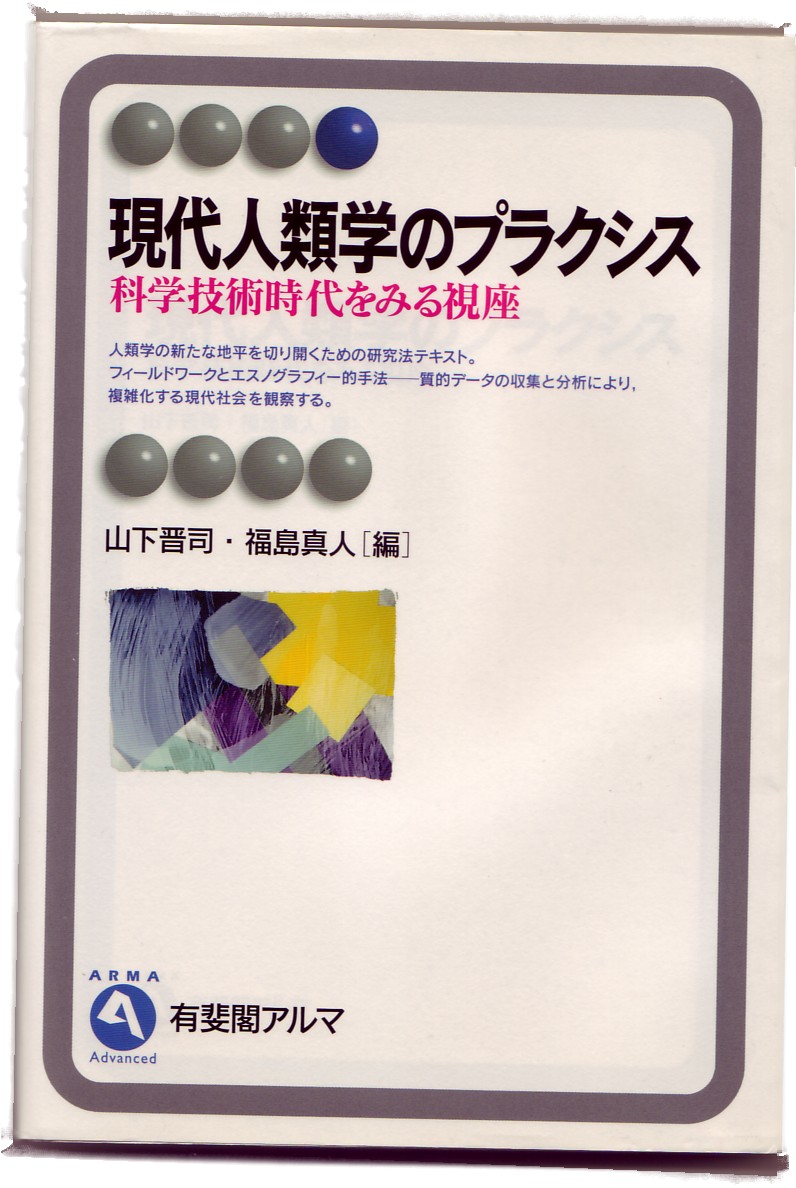
����

����
����ʸ�ϡ������ˤ��������������ؤ��������뤫���Ȥ����ơ��ޤ�ͻ������ΤǤ�������������α鵻�ϡ��Τ䤻��դ�Ω�����ʤɤ������ꡢ������ʣ������ħ���ĤΤǡ����������Τ����Ǥ��������ǡ�����ʸ�Ǥϡ������β���ʱ鵻�������Τߤʤ餺����ͥ����θ���ˤ��ܤ�ž���뤳�Ȥ���Ƥ��Ƥ��ޤ�������ˤ�äơ�������Ū�ʻ������������졢����������ؤ������ޤ롢�ȹͤ��뤫��Ǥ���
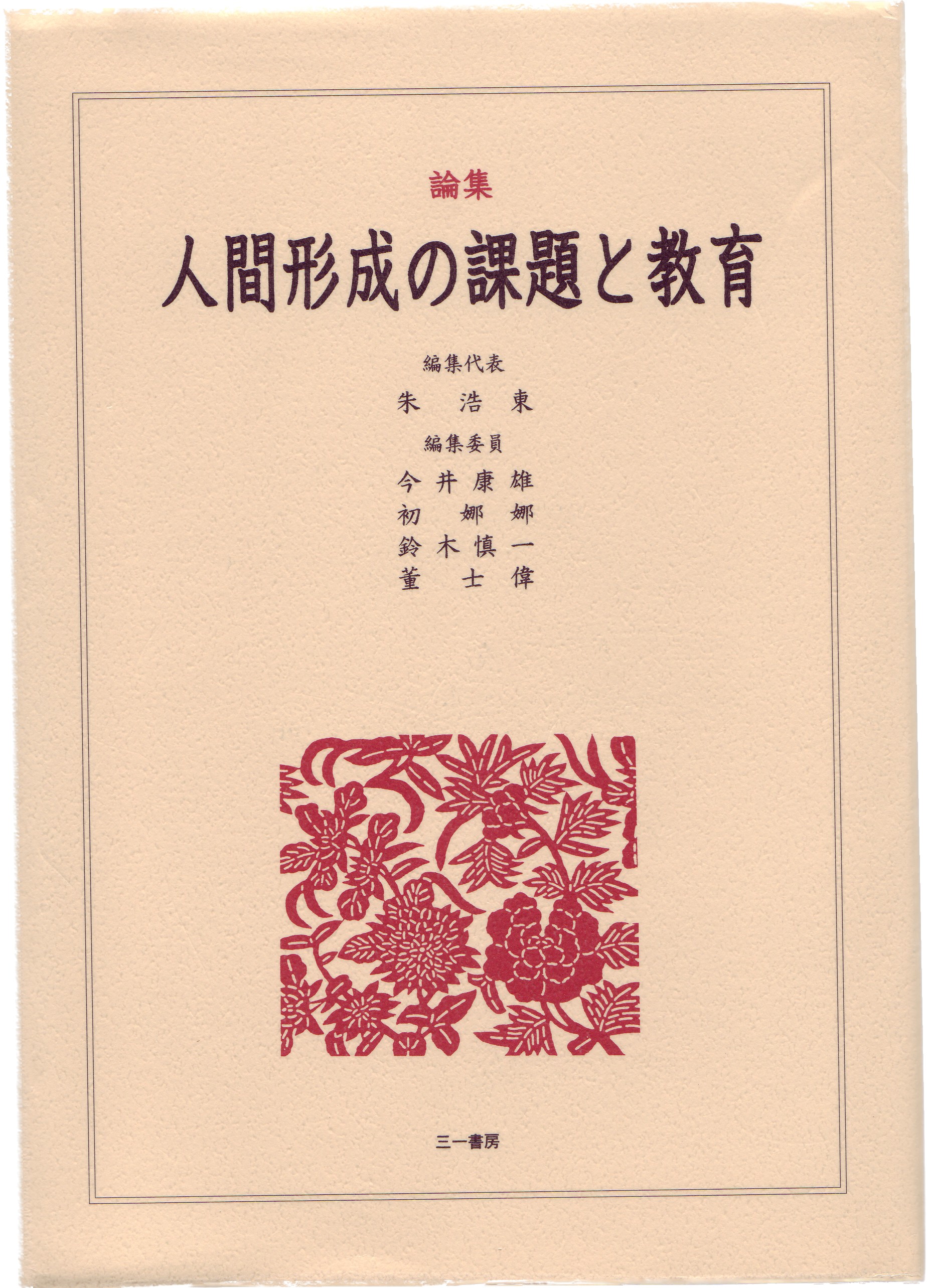
����
����ʸ�ϡ���ǽ����γع������ɤΤ褦�ʷ��ǿʹԤ��뤫���Ȥ��������ͻ������ΤǤ��������Ǥϡ���ǯ����鳦�ǽŻ뤵����Ǽ�����˾����Ƥơ����줬�������������ͥ����γع�����Ϳ����ƶ��ˤĤ���ʬ�Ϥ��Ƥ��ޤ���������Ū�ˤϡ��Ǽ�����αƶ���Ǥ�������롢�����ࡦ���Фξʵ���Ĥ���°���ع������Ȥ��Ƽ�ꤢ���������Ǥߤ�����٤˳ع�Ū�ʶ�������ν���ħ�ҡ�ʬ�Ϥ��Ƥ��ޤ���
��������������������Attractive Features and Potential Value of the Chinese Traditional Theater School as a Tourist Spot: A Case Study of the Shaanxi Opera in Xi'an City.�� Min Han and Nelson Graburn ed.Tourism and Glocalization: Perspectives on East Asian Societies, 2010, pp.55-75. Senri Ethnological Studies 76 (National Museum of Ethnology: ��Ω̱²����ʪ��)
.
����
����ʸ�Ǥϡ����ष�ĤĤ������¤������ࡦ���Фγ���������Ū�Ȥ��ơ��������ع����Ѹ��Ȥ��ƤɤΤ褦�ˤ�������Ƥ��뤫���Ȥ����ơ��ޤ��ͻ����Ƥ��ޤ����ޤ����������ع��δѸ��������ФˤɤΤ褦���Ѳ���⤿�餷���뤫���Ȥ�������ͻ����Ƥ��ޤ���
�������������裱�����Ծ�кѻ���α������������ĩ�� -- ���Фο�����ư��Ȥ�����ʸ���ηѾ���ȯŸ����졦���湯ͺ����������ۤ��ԡض���ξ���Ʊ��������2011ǯ���滳���ǡ�pp.13-28.
����
����ʸ�Ǥϡ��Ҷ����������ˤʤ�ĤĤ���Ծ�кѻ�������ǡ����פȤ�̵��θĿ���Ω��̱�ı��ع���Ĥߡ�������ؤ�������ǽ�ηѾ����Ϥ������͡��ζ�������ˤĤ��ƾܽҤ��Ƥ��ޤ���
��������������8������ʪ�۷��ߤȳع���Ω�ˤߤ�������೦�κ��Բ��� -- ������������Фλ��㤫��״����ԡ����Ҳ�ˤ�����ʸ�����Ƥν��� -- ���������벽�λ���������2015ǯ����������pp.199-224.
����
����ʸ�Ǥϡ����׳���������Ƴ�����衢�礭���Ѳ����ĤĤ������Ҳ�ǡ��������ȳ����ɤΤ褦�˺���������Ƥ��뤫������ˤ�����̵��ʸ���仺��Ͽ��ư�Ȥδ�Ϣ�ǵ��ҡ�ʬ�Ϥ��Ƥ��ޤ���
��ʸ
�����ȥ�
�������������ַ�ǽ�ع��ˤ�������ε�ˡ�ν��������ν��� -- ������»Ԥο��е��ʳع��λ�����濴�ˡס�Ķ��ʸ���ʳص��ס١������ء����ˣ�������ǯ����8�桤pp.145-166.
����
����ʸ�ϡ����ε�ˡ�Ȥ���ʸ�������Ū�ʳ�ǰ��꤬����ˡ���ͥ�ο��Τ˾����Ƥơ��ݤν��������ν���ħ��ʬ�Ϥ����ΤǤ��������Ǥϡ������������������ࡦ���Ф����Ȥ������Фα��ع��Τ���ʶ��������ʬ�Ϥ��Ƥ��ޤ�������ʸ����Ū�ϡ���ͥ�ηݤν��������ȡ��ع��ȿ��ι�¤Ū��ħ�Ȥ���ߺ��Ѥμ��֤�������뤳�Ȥˤ���ޤ���
�����ȥ�
�����������������������ˤ�����������������ζ��岽 -- �ؽ��������������鸫��������������б�ඵ��λ���ʬ�Ϥ��濴�ˡסؿ��ͽ��ر���������١ʿ��ͽ��ر���ظ����ˣ�������ǯ����50����3����pp.17-41.
����
����ʸ�ϡ���������������ࡦ���Ф����Ȥ��ơ���ͥ��������Ū����������ʬ�Ϥ����ΤǤ������Фˤ����Ƥϡ����̱������鸽�ߤޤǤΤ������ˡ�����Ū�����������ɡ����ɡ������ɡ����ع��ʤɤθޤĤΥ����פ���ͥ�����ȿ���¸�ߤ��Ƥ��ޤ���������ʸ�Ǥϡ���������ͥ�����ȿ���Ĺû����Ӥ�����ͥ�����ȿ��ζ��岽�������ʤ������ФƤ������ˤĤ��ƹͻ���ä��Ƥ��ޤ���
�����ȥ�
�����������������������ˤ�����鵻�ν��������θ���Ū������ -- ���»Ԥο��е��ʳع���¿��Ū�������롦�����Υ���ե����̤��ơסص���̱¯�١ʵ���̱¯�ز����������ǯ����20��21�桤pp.45-70.
����
����������೦�Ǥϡ�����廰�þ⡢�沼��ǯ���������λ��ô֤α鵻�ϡ����沼�λ�ǯ�֤β��Ѥߤˤ�äƻ٤����Ƥ���ˡפȤ����ʸ������ꡢ��ͥ�β��Ѥ߽��Ȥκ����ħŪ��ɽ�����Ƥ��ޤ�������ʸ�ϡ���������Ū�ʴ������顢��ͥ���ȤηθŸ��졢��ͥ�����ȿ��ι�¤Ū��ħ����ͥ�����ȿ������Ū�������Ȥ������������ܤ��ơ����γʸ����ż�����ˤȤɤޤ���ͥ���Ȥκ���̱²��Ū��ʬ�Ϥ����ΤǤ���
�����ȥ�
�������������ֳؽ��Ȥ��Ƹ�������������ο����Ū�ե�����ɥ����-- �鿴�ԤΥե�����ɥ�����Ψ�����뤿��λ����סؿ��ͽ��ر���������١ʿ��ͽ��ر���ظ����ˣ�������ǯ����51����3�桤pp.27-45.
����
����ʸ�ϡ�������������ä������ࡦ���Сˤ˴ؤ���ɮ�Ԥ�Ĵ���и����Ȥˤ��ơ��鿴�ԤˤȤäƤΥե�����ɥ���ΰ�̣�ˤĤ��ƹͻ������ΤǤ��������Ǥϡ�ǧ�βʳ�Ū�ʡֳؽ��פȤ���������Ω�äơ��ե�����ɥ�����ץ�������ͤĤ��ʳ��ˤ櫓�����Τ��줾����Ψ�����뤿�����ˡ������Ƥ��Ƥ��ޤ�������ʸ�ϡ����ͽ��ر���ؤ�ô�������Fieldwork Methods�ʥե�����ɥ�����ˡפμ��ȸ����˼�ɮ������ΤǤ���
�����ȥ�
���������������鵻�����ο����Ū�����Υ���ե����ˤऱ����--�����ε�ˡ������ߤ�������»Ԥο��ж���סر�ฦ�楻�����ס٣�������ǯ�������������ر����ʪ�ۡ���������21����COE�ץ�����ࡧ��������Ū����ȱ��ؤγ�Ω�ˡ�pp.157-168.
����
����ʸ�ϡ����ε�ˡ�Ȥ��������Ū��ǰ��꤬����ˡ���ͥ�ηݤν��������˾����Ƥơ���ǽ����Ҥ�����ˡ�����������ΤǤ��������Ǥϡ����������ࡦ���Ф����Ȥ��ơ����Фˤ�����鵻�����β��������ʳ�������������Ҳ�ط��Ȥ������Ĥ�¦�̤��鵭�Ҥ�����ˡ������Ƥ��Ƥ��ޤ�������ʸ�Ǥϡ����Τ褦����ˡ����ֱ鵻�����Υ����Υ���ե����פ�̿̾����¾�η�ǽ����θ���ؤα��Ѥ���ǽ���⸡Ƥ���Ƥ��ޤ���
�����ȥ�
�����������������������鸦�椫��ߤ���������������ඵ�顡--�����Ф���ͥ����ˤ��������ط���ʬ�Ϥ��濴�ˡסر�ฦ�楻�����ס٣�������ǯ�������������ر����ʪ�ۡ���������21����COE�ץ�����ࡧ��������Ū����ȱ��ؤγ�Ω�ˡ�pp.163-176.
����
����ʸ�ϡ��ع��Τ褦�ʸ���Ū�ȿ���������ǽ�����������Ȥ�������ط��ˤɤΤ褦����ħ���ߤ���Τ����Ȥ����ơ��ޤ�ͻ������ΤǤ�������ʸ�Ǥϡ��������ʡ����»Ԥα�������ɤȸƤФ�롢�����ࡦ���Фξʵ���Ĥ���°���ع������Ȥ��������Ǥߤ��붵�մ֤γع�Ū��ʬ���ηϤ˾����Ƥơ����줬¾��¿���η�ǽ�ˤߤ���ȸ�����Ū�ʻ���ط��ȡ��ɤΤ褦�˰ۤʤ�Τ��ҡ�ʬ�Ϥ��Ƥ��ޤ���
�����ȥ�
�������������ָ������Ρֲ��ɡפ���ħ��Ÿ����-- ��������λ��Ĥ�̱�ı��ع��ιͻ���������١ʰ�����ظ������ز����������ǯ���ʣ֣�졥33����pp.263-282.
����
����ʸ�ϡ��Ŀ���Ω�ˤ��̱�ı��ع�����ħ�ˤĤ���ʬ�Ϥ����ΤǤ���̱�ı��ع��ϡ�1978ǯ��ʸ�����̿��ˡ�������ܤ���Ω�ع���̱�ijع��ˤ���Ω���夹�붵���������ʤ���褦�ˤʤäƤ�����Ω���줿�ع��Ǥ��������ηбļ��֤Ͽ�̱���¹�η�������¸�ߤ��Ƥ���������Ū�ʲ��ɤȸƤФ����ͥ�����ȿ���������Ƥ��ޤ�������ʸ�Ǥϡ���������λ�����濴�ˡ�����̱�ı��ع��ˤɤΤ褦����ħ���ߤ��뤫�ҡ�ʬ�Ϥ��Ƥ��ޤ���
�����ȥ�
����
����ʸ�Ǥϡ��������ؤζ������ؽ���������̤˴�Ť����������������ͥ���������Ū�˸�����ȸ��������ɤȤ��������ƽ��פʸ������ηθ�ˡ�ζ������ؽ���������ħ�ҡ�ʬ�Ϥ��Ƥ��ޤ�������ʸ����Ū�ϡ������������Ϣ����Ը�������餫�ˤ���Ƥ��ʤ��ä����Ρȸ��������ɤ���ħ���Υ���ե��å��˲������뤳�ȤǤ��ꡢ��������������ࡦ���Фα��ع��Ǥζ����������λ���Ȥ��Ƥ��ޤ���
�����ȥ�
����������������Ϯ���줿�����ࡧ���ο��Сסط�ߤ�Ѥ��١ʹ�Ω̱²����ʪ�ۡ���������ǯ9��桤pp.14-15.
����
�ܥ����ϡ����ಽ���ĤĤ��ä����Ф�̵��ʸ���仺�����뤳�Ȥˤ�äơ����б�೦�ˤɤΤ褦�ʥݥ��ƥ��֤��Ѳ�������������Ҳ𤹤��ΤǤ���
�����ȥ�
������������2015���ָ��������������ع���̱²��Ū���� -- ��������»Ԥο��Ф����Ȥ��� --������������ʸ������ʡ�Ķ��ʸ���ʳ��칶��ʸ������إ�������������ʸ��pp.1-342.
����
�����ȥ�
������������2016����ʸ���仺�ݸ���IJ�����ɴǯ���ġ����°�¯�Ҥθ��ȱ� -- �ݸ�ȷѾ���ᤰ�뤢�����������Ĥγ�ƣ�ײϹ��ξ�����������������ϰ��ʸ���仺 -- ����ؤλ��������ٹ�Ω̱²����ʪ��Ĵ�����136��pp.225-245.
����
����ʸ�Ǥϡ���ǯ��̵��ʸ���仺���������������ࡦ���Ф��ݸ�ȷѾ���ᤰ�äơ��������ܥ�٥�ǤɤΤ褦������Ū���𤬤��ꡢ����ˤ�äƤ����ʤ����꤬�����Ƥ��뤫�ҡ�ʬ�Ϥ��Ƥ��ޤ���
�����ȥ�
������������2017���ֿ��Ф���ͥ����ι����붵��ʺ����������뤳�ȡ���ǰ����γع�������ħ��Ÿ�������ܤ��ơס��ϰ踦�� JCAS Review�١ʵ�������ϰ踦�����������17(1)��pp.2-21.
����











































